健康診断で「血圧が少し高めですね」と言われたことがある人も多いのではないでしょうか。その原因の一つとして挙げられるのが「塩分の摂りすぎ」。
味の濃い料理や、外食が多い現代では、知らず知らずのうちに必要以上の塩分を摂ってしまっていることがあります。
今回は、一日の塩分摂取量の目安や、摂りすぎによる影響、そして今日からできる減塩の工夫について紹介します。
一日の塩分摂取量の目安

厚生労働省が定める「日本人の食事摂取基準(2025年版)」によると、1日の塩分摂取目標量は以下のとおりです。
• 男性:7.5g未満
• 女性:6.5g未満
一方、世界保健機関(WHO)は、1日あたり5g未満を推奨しています。実際の日本人の平均摂取量は約9〜10gとされており、多くの人が目標値を超えているのが現状です。
ちなみに、食塩5gとは小さじ1弱程度。味噌汁を1杯飲むだけで1.5〜2gの塩分を摂ることもあるため、意識しないとすぐにオーバーしてしまいます。
塩分を摂りすぎるとどうなる?
塩分を摂りすぎると、体の中では余分なナトリウムを薄めるために水分をため込もうとします。これが「むくみ」や「高血圧」の原因になります。
血圧が上がることで血管に負担がかかり、動脈硬化や心臓病、脳卒中などの生活習慣病につながる可能性もあります。
また、塩分の摂りすぎは胃の粘膜を刺激し、胃がんのリスクを高めるという報告もあります。
さらに、子どものうちから塩分の多い味に慣れてしまうと、将来も「濃い味」しか満足できない味覚になりやすいともいわれています。家庭での味付けは、子どもの健康にも直結しているのです。
意外と塩分が多い食べ物

「しょっぱくないから大丈夫」と思っていても、実は塩分を多く含む食品はたくさんあります。
• パン類(食パン1枚で約0.8〜1.2g)
• ハム・ソーセージ類(1枚で約0.5g)
• インスタントラーメン(スープまで飲むと5〜6g)
• みそ汁(1杯で約1.5〜2g)
• ドレッシングやめんつゆ(大さじ1で約1g)
• チーズ・漬物・梅干し など
特に「パン」や「加工肉」は味が濃く感じにくいのに、思った以上に塩分が含まれています。また、市販の総菜やコンビニ弁当は、保存性を高めるために塩分が多く使われていることも。
外食の多い人は注意が必要です。
今日からできる減塩のコツ
① だしの旨みを活かす
かつお節や昆布、干ししいたけなどの「だし」をしっかり取ると、塩分が少なくても満足感のある味になります。和食中心の食事では、だしの力を上手に使うことが減塩の近道です。
② 酸味・香り・スパイスで味に変化を
レモンやお酢、ゆずなどの酸味をプラスすると、味が引き締まり、塩分を減らしてもおいしく感じます。
また、こしょう・しょうが・にんにく・ハーブなどの香りやスパイスも、塩分を控える助けになります。
③ 調味料を「かける」から「つける」へ
しょうゆやソースを料理全体にかけるよりも、「少量をつける」方が使用量を減らせます。

食卓に小皿を用意しておくと、自然と意識できそうですね
④ 加工食品を控えめに
ハムやベーコン、漬物などの加工品は塩分が高め。どうしても使う場合は量を減らし、野菜や果物を多めにとるようにするとバランスが整います。
減塩調味料・食品の上手な選び方

スーパーでも「減塩しょうゆ」「減塩みそ」「無添加だし」など、減塩商品が増えています。
ただし、減塩と書かれていてもナトリウムが完全に少ないとは限らないため、「栄養成分表示」で塩分量(食塩相当量)を確認することが大切です。
また、ラベルに「ナトリウム〇mg」と書かれている場合は、以下の式で塩分量を換算できます。
食塩相当量(g)= ナトリウム(mg) × 2.54 ÷ 1000
表示を見慣れてくると、どの食品にどれだけの塩分が含まれているかが感覚的にわかるようになります。
まとめ
塩分は私たちの体に欠かせないミネラルですが、摂りすぎは健康に大きな影響を及ぼします。
「少し味を薄くする」「だしや酸味をうまく使う」など、ちょっとした工夫を積み重ねることで、無理なく減塩生活を続けることができます。
毎日の食事を見直して、健康的においしく塩分コントロールしていきましょう!
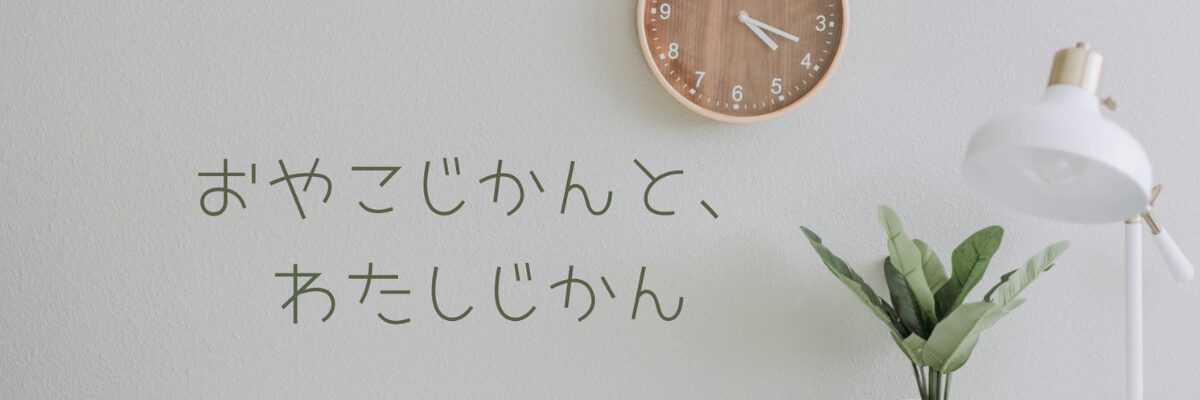
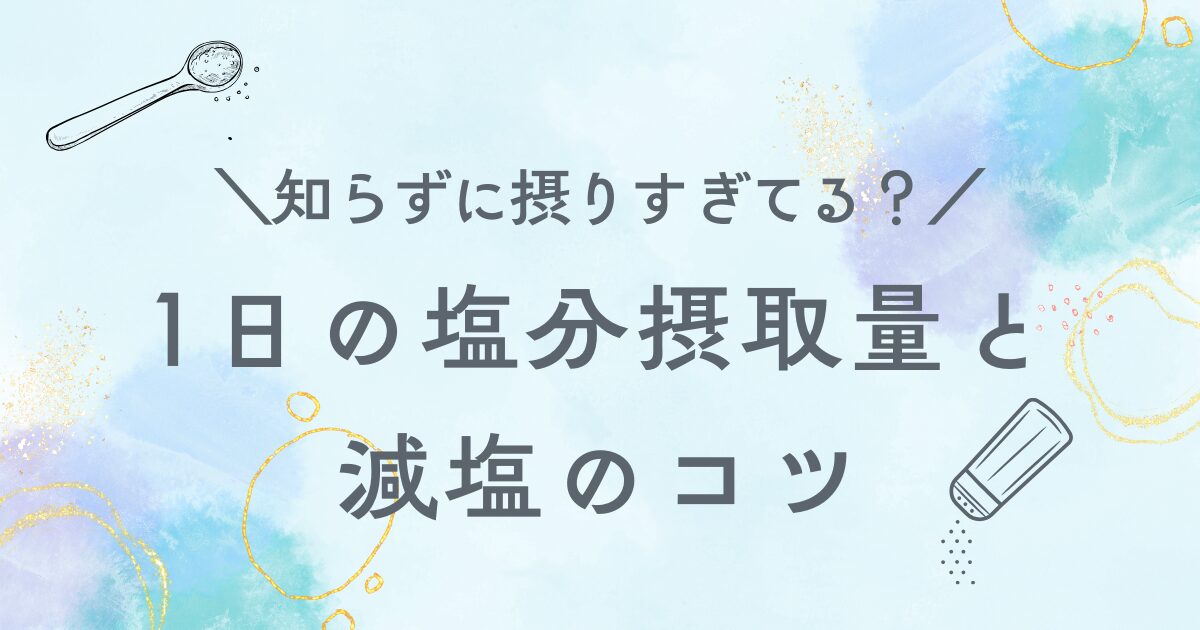
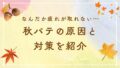

コメント