「無添加がいいってよく聞くけど、そもそも“添加物”って何?」
「子どもには安心・安全なものを食べさせたいけど、どう選べばいいの?」
そんなママの疑問やモヤモヤにお答えするのが、今回の記事です。
食品添加物は、食べ物を長持ちさせたり、色をキレイに見せたりするために使われていますが、子どもにはできるだけ避けたいものもあります。
この記事では、よく使われる添加物の中から、特に気をつけたいものをまとめました。
添加物とは?
食品添加物とは、食品を加工・保存する際に使われる化学物質のこと。
「保存料」「着色料」「香料」「甘味料」「酸化防止剤」など、目的ごとにさまざまな種類があります。
中には自然由来のものもありますが、多くは人工的に合成されたもので、体への影響が心配されているものもあります。
すべてが悪いというわけではありませんが、特に成長期の子どもには慎重に選びたいですね。
子どもに気をつけたい添加物 5選
- 合成着色料(赤色◯号、青色◯号など)
お菓子やジュース、アイスなど、カラフルな商品に使われがち。
発がん性やアレルギーとの関連が指摘されており、EUなどでは一部規制されている国も。
→ 見分け方: 原材料名に「◯色◯号」と記載あり。
- 人工甘味料(アスパルテーム、スクラロースなど)
“カロリーゼロ”と表示されたガムやゼリー、飲料に多く使われます。
甘さは砂糖の数百倍にもなり、味覚の発達に影響を与える可能性も。
→ 見分け方: 「アスパルテーム」「L-フェニルアラニン化合物」などの表示に注意。
- 保存料(ソルビン酸、安息香酸など)
お弁当やお惣菜、漬物などの日持ちを良くするために使われます。
腸内環境への影響やアレルギーの原因になることも。
→ 見分け方: 「ソルビン酸K」「安息香酸Na」などの表示。
- 亜硝酸ナトリウム(発色剤)
ハムやウインナー、ベーコンなどの加工肉によく使われ、ピンク色をキレイに保つための添加物。
過剰摂取で発がん性物質に変化するリスクが指摘されています。
→ 見分け方: 「亜硝酸Na」と記載されていることが多い。
- 化学調味料・香料(グルタミン酸ナトリウムなど)
うま味を強く感じさせる添加物で、スナック菓子やレトルト食品などに広く使用。
「もう一口食べたい!」と感じさせる中毒性があり、自然な味覚が育ちにくくなる心配も。
→ 見分け方: 「調味料(アミノ酸等)」「香料」といった表記。
添加物の見分け方・ラベルのチェックポイント
スーパーなどでパッケージを見るときは、原材料名をチェックするクセをつけましょう。
表示の順番は、含有量が多い順に並んでいます。
また、「無添加」と書いてあっても、“保存料無添加”だけで他の添加物が入っていることもあるので注意が必要です。
なぜ子供によくないの?

子供の体は大人に比べ小さくて、まだまだ発育の途中です。体の中で食べ物を分解したり、いらないものを出したりする力も、まだ十分ではありません。
だから、添加物が体に入ったときに、その影響を受けやすいんです。
とくに、着色料や保存料、あまい人工甘味料などは、体の中にたまりやすく、少しの量でも体に負担がかかることがあります。
また、こどもの脳は今まさに成長中。一部の添加物には、気持ちが不安定になったり、集中しづらくなったりするものも、あるといわれています。
さらに、子供の頃に、強い味・濃い味に慣れてしまうと、素材そのままのやさしい味を、おいしく感じにくくなってしまうことも。
これから先の食生活にもつながる、大事な時期なのです!
完全に避けなくても大丈夫!「ゆる無添加」のすすめ
全部の添加物を避けようとすると、正直とても大変。
ですが、できるだけ避ける・なるべくシンプルな素材のものを選ぶだけでも、子供の体にはとっても優しい選び方になります。
ママのストレスにもなってしまうので、「なるべく減らす」くらいのゆるさでOK!
- よく食べるお菓子やお惣菜だけ、添加物を気にして選ぶ
- “週末だけは無添加Day”など、できる範囲で工夫する
- 手作りや、素材がシンプルな商品を選ぶ
大切なのは、「知って選ぶこと」。それだけで安心感がぐっと違ってきます。
おわりに
子どもたちのカラダは、日々の食べ物でできています。
無理をせず、でもちょっとだけ意識して、「できるだけシンプルなものを選ぶ」。
それだけでも、家族みんなが健康で元気に過ごせる毎日に近づけるはずです。
「市販の無添加おやつ」も紹介しているのでもしよければご覧ください♪
健康志向さんのための油の選びかた
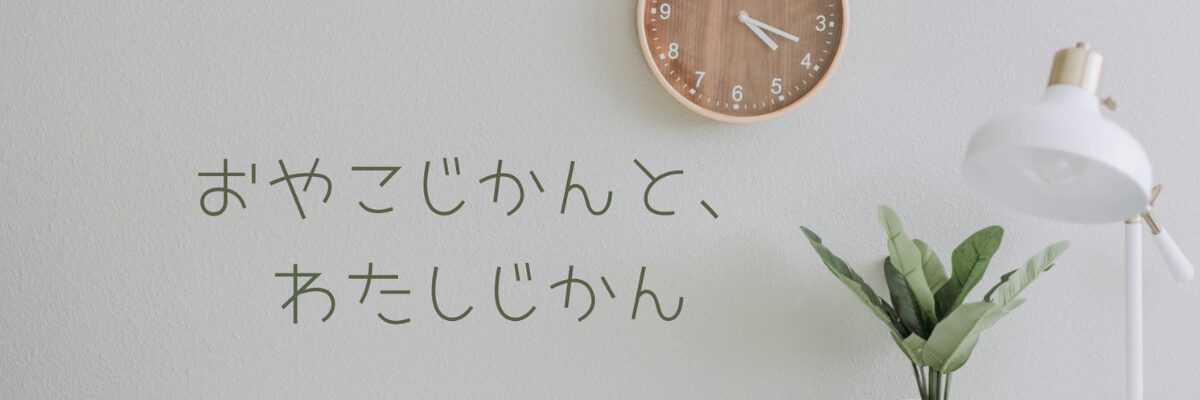
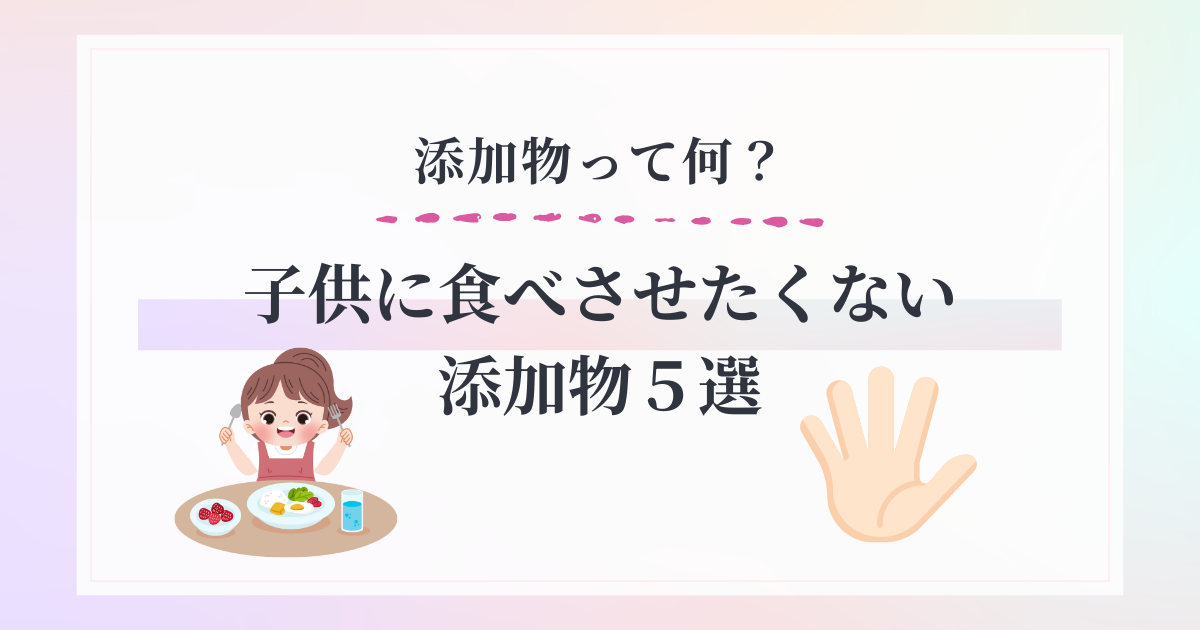
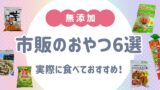
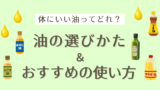
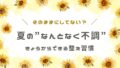

コメント